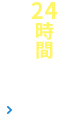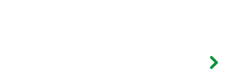徒然想 第九回
平成31年03月5日
色見えて 移ろふものは 世の中の
人の心の 花にぞける
小野小町
寒冷の北風にさらされて、どこかに行っていた木の葉や、木の実が、こぞって帰ってくるにしても、遅々として進まない時期を “早春”と呼ぶ。やがて、木立の下から、すき透るような木の葉を見上げる向こうに、青い空を仰ぐことができる。
その頃からが本格的な春の訪れである。
目に青葉 山ほとどきす 初がつお
元禄の俳人・山口素堂の有名な句である。
この俳句は、もの皆芽ぐむ春から、光りあふれる夏へと、日本中の野が、まみどりになる時期になると、 どこかで、 必ずお目にかかる名句である。
四季折々、時の移ろいとともに、姿を変えていく自然。
日本人は、その推移の中に独特の美しさを見だし、 自らの思いを託してきた。
ところが、この俳句は「青葉」「ほととぎす」「かつお」と季語が多く、優秀な作品とは言えない、という批評もあるそうである。
ところで、私が東京に住居を構えていた頃、行きつけの鮨屋は決まっていた。その理由は二つあった。
一つは、その鮨屋の親方が博学だった事である。
「初物食いは、七十五日の長生き」とか、のたまって、鰹に関するうんちくを、傾けるのである。
“江戸っ子は、初鰹に目の色を変えた。初鰹は夏の季節の先ぶれ、関東では刺身で、土佐では、たたきで食べる。
サバ科の回遊魚で、黒潮上層部を群泳しているが、土佐を経て、紀州沖へ、かかるあたりでは、まだ脂がのっていない。
それが伊豆半島を回り、相模灘へ入った頃から、いい脂ののり具合になる。
魚味の熟した関東では、一瞬を惜しんで刺身で賞味することが、江戸っ子の胸を躍らせたのである・・・”といった具合である。
もう一つの理由は、人の気をそらさぬ上、私と気の合った感性を感じた親方だったからである。
ある時、私が、「親方、八本のタコの足にも、旨いのと、それほどでも無いのとあると聞いたけど、本当かね?」
と聞くと、親方、よくぞ尋ねてくれたとばかりに、大得意になって、「タコの足の中で、旨いのは、吸口の両側に近いところの二本が最上。
反対側の眼の近くの二本は最低」と教えてくれた。 しばらくして、友人と店へ行き、つけ台の前に座って、親方の包丁さばきを見ていたら、 私の視線を感じてか、私の顔をじっと見て、 やおらタコを吸い口のところから、パっと切り落として握ってくれた。
そして友人には、サッと反対側の、眼の近くの足を、 何事もなかった顔をして、 握りながら、私の顔を見て、ニヤっとするのだった。
この親方に “キラッと光る” 粋な計らいがある限り、どうしても他の鮨屋には行く気がしなかったのである。
里村 盟